*2025年1月に投稿した記事に奈良旅行の際の影向の松を実際に見てきたので、写真と説明を追記しました。
こんにちは。
先日、能と狂言を観賞して参りました。
解説・字幕・質問コーナーありのホールでの開催で、初心者としては大変分かりやすく、正式(?)な能よりも注目すべきところや、内容が分かり、楽しめました。
今回、質問もできたので、お能に関係する樹木について知ることが出来たのでまとめたいと思います。お能に行く際に、注目してみるのも楽しいと思います。
舞台は
檜舞台と言われるように、ヒノキで作られています。
ヒノキは日本書紀にも出てきており、スサノオの胸毛がヒノキになり、宮殿の材木に使えと言ったそうです。法隆寺もヒノキで作られ、1300年も健在ですし、素晴らしい樹木の一つですね。
鏡板(舞台の背景)には
マツが描かれています。こちらは、能といったら松の絵が思い浮かぶ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
奈良の春日大社の影向(ようごう)の松がルーツとされているそうです。
平成7年に枯れてしまいましたが、今もその名残を残しています。この松の前で観阿弥世阿弥も舞ったようですね。この代わりに鏡板で松が描かれたとのこと。順番が面白いです。

2025.11 春日大社 影向の松
因みに、横浜能楽堂の鏡板には梅も描かれているそうです。これは、旧加賀藩主前田邸に建てられ、前田家の祖が菅原道真だったことから梅が描かれたとされています。面白いですねぇ。
また、橋掛かりと言われている、観客席から見て左手にある廊下のようなところに3本松が植わっていますが、これは舞台に近づくほど大きくなり、遠近法を使っているそうです。よくよく見ると納得しました。お能初心者からすると、大変面白い話でした。
舞台の右側には
タケが描かれています。
囃子方のお道具は
笛は竹で作られており、
太鼓はケヤキで、小鼓はサクラの木で作られているそうです。
樹木で作られていることも面白いのですが、それぞれ、良い音になるまで100年以上かかるそうです。。。今回の舞台で使われたのは江戸時代末期くらいのものかなぁと話しておられ驚愕しました。
クラシックに詳しい友人曰くストラディバリウスと同じとのこと。こちらも17世紀くらいに作られているのですね。
最後に
私の大好きな、樹木と絹と美しいものだけで構成されているお能と狂言、あと、笛と太鼓の何とも言えないリズム、たまらない空間でした。
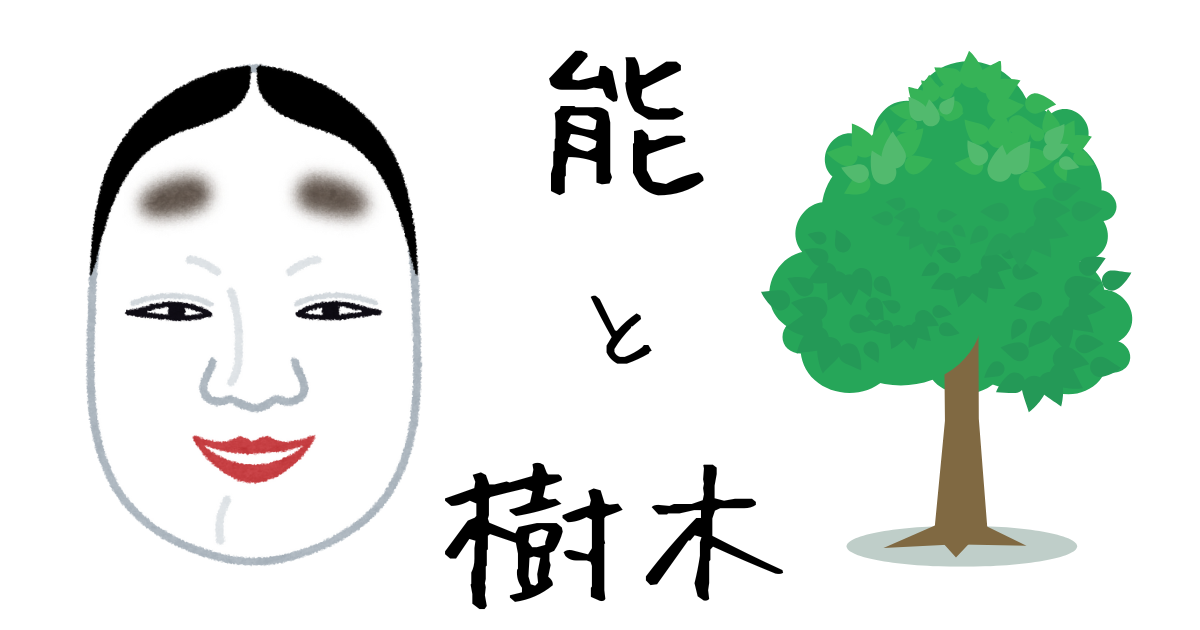
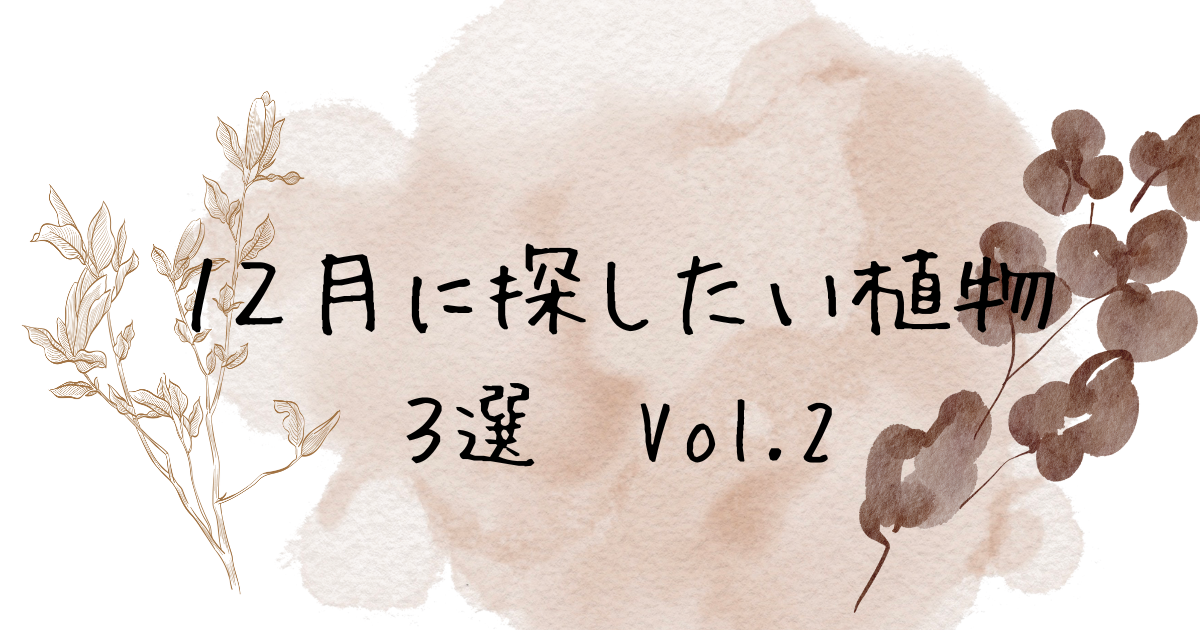

コメント