はじめに|鑑賞だけではない秋の七草
秋の七草といえば「萩・葛・桔梗・撫子・女郎花・藤袴・薄」。
春の七草が「食して無病息災を願う」のに対し、秋の七草は「目で愛でる草花」として知られています。
去年の記事では、写真と説明を主に記載しています。Are you ready for 秋の七草? – 日本の植物
昔の人々にとって七草は単なる観賞用ではなく、薬や食、祭祀、生活の知恵としても欠かせない存在でした。
今回はそれぞれの草花の「昔の使われ方」に注目してご紹介します。
見ごろ時期
「秋の七草」と言いますが、実際咲く時期はバラバラです。
まず、最初に咲くのはナデシコとキキョウでしょうか。
夏の盛りの6~8月にもお目見えします。
そして、8月の終わりからクズの花が見られます。
現代では秋と言える9月にかけてハギやオミナエシ、フジバカマやススキといった具合でしょうか。
撫子(ナデシコ)|歌に詠まれ、薬草としても
「大和撫子」の名で知られるように、その可憐さから和歌や古典に数多く登場する撫子。
薬草としては利尿作用や止血の効能が知られ、民間療法にも用いられました。
愛らしさと実用性を兼ね備えた草花です。

25年8月 青森県竜飛岬周辺にて
また、ナデシコは万葉集で「奈泥之故」などと表記され、「撫でたいほどかわいらしい花」というところからの名前のようです。ナデシコは花期が長いため、「常夏の花」という異名があり、『源氏物語』では(常夏)の帖があります。
山がつの 垣ほに生ひし 撫子の もとの根ざしを 誰れか尋ねむ
また、『枕草子』では絶賛された草花の一つです。
桔梗(キキョウ)|咳止め薬としての桔梗根
秋の七草のひとつ、桔梗の根は桔梗根(ききょうこん)と呼ばれ、昔から咳止めや去痰薬として利用されてきました。
可憐な青紫の花は観賞用として愛される一方、薬草としての役割も大きかったのです。



6月の単衣に単体のキキョウ模様があしらわれたものを着ることもあるそうです。先取りの文化ですねぇ。
葛(クズ)|薬・食・繊維を生み出す万能植物
葛の根から作られる葛粉は、和菓子や料理に欠かせない素材。
また、漢方薬「葛根湯」にも使われるように、発熱や風邪の初期に効く薬効を持っています。
さらに、葛の繊維は糸や布としても利用され、生活全般に役立つ植物でした。



奈良好きの身としては、「吉野の葛」ということで行って参りました。25年5月に薬草園の方にも行って参りましたが、植物好きにはたまらない場所でした。まだ記事に出来ていなかったので、整理したいと思います。
森野吉野葛本舗 | 【吉野葛の販売・通販・お取り寄せ・卸売・レシピのご案内】
あの藤原道長も糖尿病の薬として服用していたとされる説もあります。


萩(ハギ)|秋の代表花と萩箒
萩は日本原産の植物で、「秋の花」として万葉集にも最も多く詠まれる植物です。


亀戸の龍眼寺はハギ寺と呼ばれるそうですね。初夏に伺いましたが、この時期にも足を運びたいものです。


女郎花(オミナエシ)|供花と薬草の二面性
黄色い小花を房状に咲かせる女郎花は、秋の供花として寺社や仏前に飾られることが多くありました。
また根は敗醤(はいしょう)と呼ばれ、利尿薬や解毒薬として使われた歴史もあります。
オミナエシの織色目では、経糸が青で横糸が黄色で表現するものもあるそうです。もう少ししたら、こういった色目の着物を纏いたいですね。実際、『源氏物語』でも野分で童女装束の「汗衫(かざみ)」がオミナエシ色で、東屋では「オミナエシの織物」が登場します。


藤袴(フジバカマ)|香料としての七草
藤袴はその香りが珍重され、乾燥させて香袋や衣類の防虫に利用されました。
葉に桜の葉と同様にタマリンという芳香族化合物が含まれていて、乾燥させると桜餅のにおいがするようです。
平安時代には香りを楽しむ風習があり、藤袴は雅な暮らしに欠かせない草花だったのです。





未だにヒヨドリバナとの違いに悩みます。。。以下はヒヨドリバナ?


薄(ススキ)|月見と生活素材
秋の月見に欠かせないススキ。
その葉や茎は茅葺き屋根の材料や家畜の飼料として使われ、農村の暮らしを支えました。
観賞と実用の両面で親しまれた植物といえます。

おわりに|七草の知恵を今に生かす
秋の七草は、単に秋を彩る花々ではなく、薬や食、祭祀、暮らしの道具として人々の生活に深く結びついていました。
現代では鑑賞の側面が強いですが、その背後には先人たちの知恵と暮らしがあります。
秋の野に咲く七草を見かけたら、そんな昔の使われ方にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

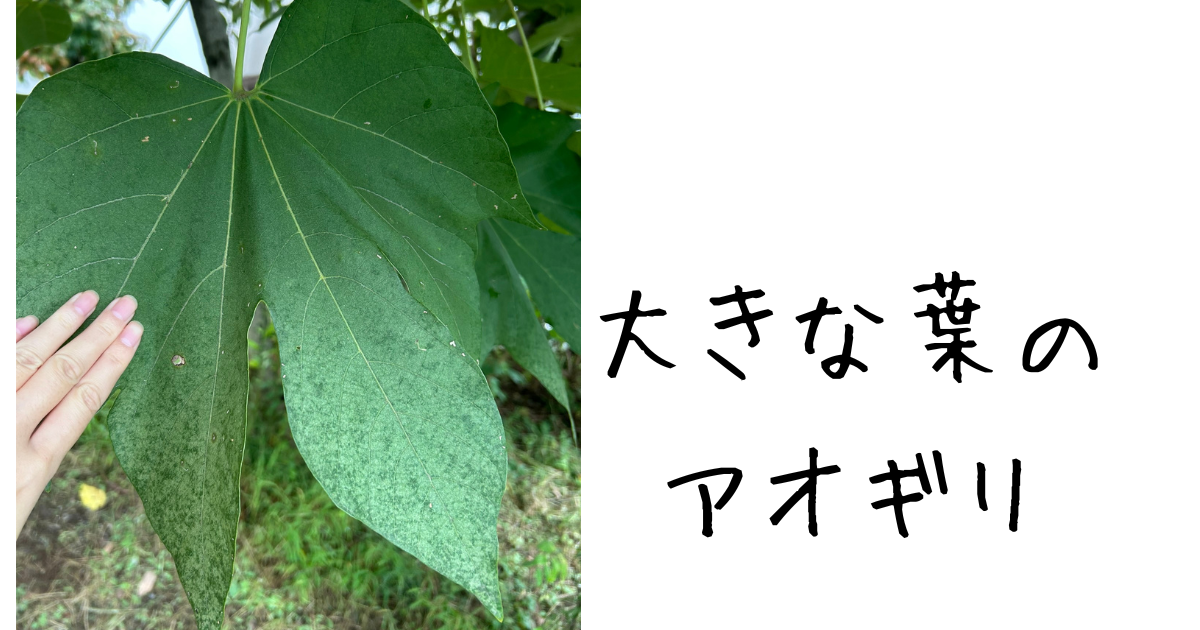

コメント